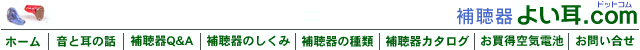
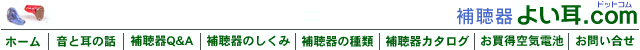
混合性難聴は現在の医学で治療が可能ですか? |
|
混合性難聴は、音を伝える部分(鼓膜や耳小骨など、外耳から中耳にかけての部分)が原因の伝音性難聴と、音を感じる部分(内耳、聴神経部分)が原因となる感音性難聴が組み合わさった難聴です。 伝音性難聴に関しては、人工の耳小骨や鼓膜再生手術などで治療が可能ですが、感音性難聴についてはまだまだ多くの課題があるようです。 人間は音を内耳蝸牛内有毛細胞にて感知をしていますが、入力される音の成分をおよそ1万5千という非常に細かい単位に分け、音質等の分析を行っています。 感音性難聴は、この有毛細胞の破壊や変異による聴覚障害ですが、近年ではこれに代わる人工内耳の開発が進み、これまで難しいとされてきた重度感音性難聴の症例にて大きな成果をあげています。 しかし人工内耳で音を分析する単位は、人間の1万5千に対し1〜数個と大変少なく、会話の声から誰が話しているのか、音楽でもどんな楽器が演奏されているのかといったことをより良く知るためには、今後器機の進化が待たれます。 聴覚障害の治療結果に関して、「音がするのがわかるようになる」、「何を話しているのか分かるようになる」といったように色々なレベルがあり、それぞれ「危険察知能力の回復」、「会話などコミュニケーションの回復」という重要な意味を持ちます。ただし特に感音性の難聴については、「もともと聞こえていたのと全く同じようになる」ことは、現時点ではなかなか困難です。 もし混合性難聴の医学的治療を検討されているのであれば、現在の耳の状態から、どのような処置が適切、または適用可能であるか(外科的手術、投薬、補聴器の装用など)、またその結果、前述したようにどのような状態に回復することが可能なのかを、耳鼻科医にてご質問、ご相談されることをお薦めいたします。 上記内容はメールにてご質問をいただいたものへのお返事ですが、返信先アドレスが不明のため、勝手ながらQ&Aのコーナーにて紹介をさせていただきました。 |