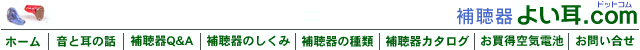
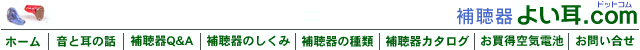
| HOME > 補聴器Q&A・よくある質問 | |
補聴器Q&A・よくある質問 |
 |
耳かけ型のオープンタイプ補聴器について教えて下さい。 |
|
「オープンフィッティングってなんですか?」に記述したように、位相反転技術によるオープンフィッティングは、こもり感、自声の響きの原因となる「外耳道閉鎖効果」を抑え、快適な補聴器装用を可能にするものと、大きな期待を背負ってスタートしました。ただし、位相反転も万能ではありません。当初注目された耳あな型補聴器のオープンタイプでは、適用できる聴力が極めて限られていたため、すべての人がこの恩恵にあずかるという訳にはいきませんでした。 ハウリングの抑制と耳あなを塞がないこと。これは相反する要素であり、いかに位相反転のハウリング抑制といっても、その効果は限定的です。そこで信号処理での限界をカバーするため、補聴器の音響的特性に注意が向けられるようになります。 これまでの補聴器開発の流れは、「小型化」にありました。「補聴器はなるべく目立たない方が良い」というニーズにより、ポケット型補聴器サイズから耳かけ型補聴器へ、それが耳あなにすっぽりと納まる耳あな型補聴器となり、さらに完全に外耳道内に納まってしまうCICサイズ耳あな型補聴器にまで発展しました。 この小型化の過程では、様々な問題も生じてきます。特に大きなものとしては、「ピーッ」というハウリングが発生しやすくなることでした。 補聴器のハウリング発生には「音を集めるマイクと音を発するレシーバーの距離」、「音の増幅量」、「ベントの長さと径」、「増幅する周波数」など様々な要素が影響を与えます。中でもマイクとレシーバーの距離はベントとともに大きな影響を与えやすく、小さくするためには耳を密閉しなければいけないことになります。 これまで補聴器は、「ある程度聴力の低下が生じている方」を前提と、製品が開発されていました。補聴器を装用して耳を塞ぐと「外耳道閉鎖効果」が生じ、低域の音が塞がれた耳あな(外耳道)の中で共鳴により増幅されますが、これまでの補聴器を必要とされるユーザー層にとっては、その低域の増幅も補聴効果の一つになったり、増幅する周波数のバランスにより、こもり感、自声の響きという問題は、ベントの利用と合わせ吸収することができました。 それが現在、多様化する社会でコミュニケーションの内容も高度化する中、補聴器を利用する方にも変化が生じてきます。 「低域〜中域は聴力低下がないけれど、高い周波数の音だけ少し聞き取りづらい」というように、これまでなら補聴器装用を考えもしなかったような聴力の方でも、コミュニケーションツールとして積極的に補聴器を検討されるようになり、こうした「聴力の一部が少し低下してきた」という新しい補聴器ユーザー層では、これまでは顕在化しにくかった「こもり感」、「閉塞感」が大きな問題になってきました。 これまでは補聴器に大きなベントを設ける、つまり塞いだ耳に穴を開けることで、ベント効果の改善を得ようとしていましたが、より広いオープンフィッティングの適用を目指し、「耳を塞がない」という試みが行われます。「鼓膜になるべく増幅音の出口を近づけ、音が鼓膜に到達する間の減衰を減らし、小さな増幅量で必要な情報を伝える」、またその「音の出口と音の入り口(マイク)の距離を遠くすることで、漏れ出した音がを再度マイクが拾うことを抑えハウリングを抑制する」といった取り組みですが、これを実現するため、一時は耳あな型に主役の座を譲っていた耳かけ型補聴器に注目が集まります。 位相反転技術に加え、耳の中での音響特性を見直すことで、耳あな型でのオープンフィッティングに対し、より快適な装用感、広い調整幅が得られるようになり、軽度難聴から中度難聴の方でも、適用できるケースが拡大しました。耳かけ型の短所とされていた「目立ちやすさ」という点も、本体サイズを小型化した上、耳へ音を導くトーンチューブを極細にすることで、スマートな装用を実現しています。以前では細いトーンチューブが増幅した音を減衰させてしまいやすいといった問題もありましたが、チューブの音響特性を補聴器のDSP(デジタルシグナルプロセッサ)側で補正ができるようになり、高い装用感と目立ちにくさの両立が可能になりました。 耳かけ型ならではの特性として、本体サイズによる多機能化のしやすさがあります。雑音下における会話の明瞭性向上、様々な環境への対応を計るため、補聴器メーカー各社では騒音抑制技術の開発を進めています。 その中のひとつ、マルチマイクによる騒音抑制では、補聴器に複数のマイクを設け、それぞれのマイクに入力されるわずかな時間的・音量的差からマイクに指向性を持たせ、顔の向いている方向の音に集中したり、移動する音源の追跡を行うことで会話音との切り分けをする、といった取り組みがされています。 これまではなるべく目立たないというテーマから、耳かけ型のサイズは弱点とされてきましたが、マルチマイクによる騒音抑制を行う場合問題となるのがそのサイズ。物理的にマイクを補聴器に配置するスペースがあるかということに加え、マイク間の距離もその効果に大きな影響を与えます。耳あな型補聴器でもマルチマイクを持つ機種はありますが、どうしても形状に制限され、耳かけ型同様の効果を目指すと、かえって補聴器が大きくなり目立ってしまうといったこともあります。 サイズによるメリットは電池寿命にも現れます。位相反転によるハウリング抑制や、マルチマイクから入力される音声信号の複雑な処理には、どうしてもDSPの高機能化が必要となり、消費電力も大きくなります。超小型のCICサイズ補聴器で利用されるPR536(10AE)に対し、耳かけ型で広く利用される電池PR48(13AE)は、容量にして倍以上の差があるため、ランニングコストといった点でも、耳かけ型の優位性は高まります。 新しい取り組みの耳かけ型オープンタイプ補聴器も、現在では各社から用途に応じた機種が発売されるようになり、既存の補聴器とあわせ、特に軽度難聴においてニーズに合わせた補聴器選択の幅が大きく広がっています。 |
mail:4133@suyama.co.jp 電話(03)3549-0755 / FAX(03)3549-0760(須山補聴器銀座店) よい耳.com Allrights reserved. |